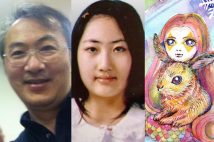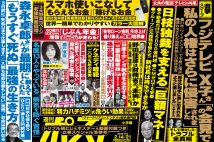使い捨てソフトコンタクトレンズが発売された1991年以降、装用者が急増、国内では1500万~1800万人がコンタクトレンズを使っていると推計されている。コンタクトレンズは高度管理医療機器で薬事法の規制対象だが、アメリカと違い日本では処方箋なしで購入できる。
このためインターネットや通販などで、眼科に通院したかのように申告し、購入している例もある。眼科検査を受けず自分の眼のカーブに合わないレンズや度数が違うレンズ、酸素透過性(とうかせい)の低い製品を使用することで、視力の低下やコンタクトが原因の障害を訴える人が増加している。
道玄坂糸井眼科医院(東京渋谷区)の糸井素純院長に話を聞いた。
「コンタクトレンズ眼障害は、一時減少傾向にあったのですが、インターネットや通販での購入やカラーコンタクトレンズの登場で、眼にトラブルを抱える方が急増しました。私の知る限り、カラーコンタクトレンズの95%以上は酸素透過性が低い素材が使用されており、さらに色素が付着しているために眼の酸素不足を起こしやすく、様々な障害が発生しています」
酸素透過性が著しく低いレンズは、角膜が変形する円錐(えんすい)角膜や角膜の内側の角膜内皮細胞が徐々に脱落する角膜内皮障害を生じたり、角膜の慢性的な炎症で、視力が徐々に低下することもある。またカラーレンズをファッションとして使用している場合は、様々な色のレンズを使うため管理が悪く、細菌感染による角膜浸潤(しんじゅん)や角膜潰瘍などを起こすことも多い。
■取材・構成/岩城レイ子
※週刊ポスト2014年3月28日号