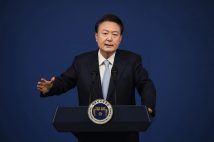死の瞬間の在り方として日本人が理想としているのが、直前まで元気でいて、苦しむことなく息を引き取る“ピンピンコロリ”だ。東大病院放射線科准教授で、緩和ケア診療部長の中川恵一医師はこう語る。
「がんで死ぬのが、まさに“ピンピンコロリ”です。私は、できればがんで亡くなりたいと思っています」
厚生労働省によると、2008年度のがん死亡者は約34万人だった。日本人の2人に1人ががんになり、3人に1人がこの病気で死ぬ勘定になる。
「ただし、それには十全な緩和ケアが必要です」(中川医師)
緩和ケアでは、抗がん剤や放射線治療などだけでなく、医療用麻薬を用いて肉体の痛みを除去する。
「がんの痛みは不要な痛みです。モルヒネで中毒になる、早く死ぬというのはウソで、かえって痛みを取ったほうが長生きします」(同)
緩和ケアは、患者の落ち込みや怒りなど“心の痛み”も癒し、残された人生をどう充実させて生きるかを考え、実践していく。
「昨秋に亡くなった元日ハム監督の大沢啓二さんがその好例になります」(同)
大沢氏は他の病院で免疫治療を受けていたが、中川医師のもとへセカンドオピニオンを求めてきた。
「大沢さんは免疫療法を中止し、放射線治療を受けた後で、私と雑談を交わす緩和ケアを始めました。彼は死の2週間前までテレビに出演しています。歌いながら登場し、歯切れよくコメントする大沢親分を観て、末期がん患者だと見抜いた視聴者は少なかったはずです」(同)
おそらく彼は死の直前まで元気だったはずだ――中川医師は推測する。
「がんの緩和ケアがうまくいくと、臨終の間際でも話ができます。そんな病気は他にありません。いわば人生の最期まで有効に活用できるわけです」
また、このところ、「死の瞬間」にどんな感情を抱いているかを検証する研究も進みつつある。例えば、最後に何を見て死んだのか――。元東京都監察医務院長の上野正彦氏はこう話す。
「死の瞬間の映像を調べることは、理論上はできなくもない。網膜に光の濃淡が焼き付くのは、ロドプシンという物質の反応によるものです。網膜を取り出し検査したら、殺人者の顔が浮かび上がるかもしれません」
※週刊ポスト2011年1月21日号