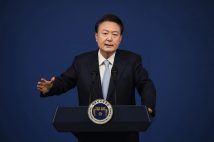世界中の紛争地域を旅する戦場ジャーナリストの桃井和馬さん(48)が、最愛の妻・綾子さんをくも膜下出血で亡くすまでの看取りの10日間を赤裸々に記録した慟哭のノンフィクション『妻と最期の十日間』(集英社新書/777円)。
著者の桃井さんが語る。
「ぼくは何もできない人間で、お金や家のことは妻に任せてきました。どこに何があるのかもわからない(苦笑)。正直な話、妻の容体とともに、病院にかかる費用や今後の生活への不安も膨らむばかりでした」
極限状態でもできる限りのことはした。「人間は自然の一部」という妻の信念を尊重し、延命ではなく自然な形で死を受け止めたいと医師に伝えた。冷静になろうと頭を“取材モード”に切り替え、妻の容体、医師や看護師の言葉、うろたえる娘の様子、見舞い客とのやりとりなどをできるだけ書き留めるようにした。
「書くことを通じて、短いけれどこの最期の日々で、最低限の、本当に最低限ですが、受け入れる準備ができました」
別れが訪れたのは発症から10日目だった。覚悟はしていたが、桃井さんの心にはポッカリと大きな穴が開いた。死後1年間は、キッチンドランカーに近い状態になった。
どん底から抜け出そうと、書き留めたメモを基に妻との最期の日々をまとめ始めたが、それはとてもつらい作業だった。執筆のため妻の日記を読み直すたびに涙がとめどなくあふれる。壊れた体と心を抱えて四国遍路に5度赴き、白装束に身を包んで朝から晩まで山道を歩いた。帰京すると机に向かい、少しずつ筆を進める。3年もの間、もがき苦しみ、ついに本書が完成した。
「この本を書かないと前に進めないと思いました。ありのままを隠さず書こうとしたからこそ、執筆は地獄のようにつらかったけど、尊敬する妻に対する責任から、彼女の死の意味が間違って伝わるような失敗はできなかった。
原稿を何度も見直して、自分の心の襞まで言葉にすることで憑き物が落ちました。表に出ることを嫌がった妻も、この本は応援してくれたはず。これでぼくも、再出発することができます」
※女性セブン2011年2月17日号