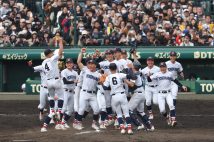船戸与一氏の書斎
性別以外、年齢、国籍、本名もすべて不明。ただいえることはこの男に銃口を向けられたら最後。誰も生きては帰れない――。
世界中を舞台に活躍する凄腕スナイパーが主人公の劇画『ゴルゴ13』(さいとう・たかを作)。1968年に始まった連載は現在、『ビッグコミック』で509話を迎えた。その膨大な作品群の中でも特に人気の高いエピソードが、作家・船戸与一氏(67)によって小説『落日の死影』(小学館刊)として生まれ変わった。
1979年に作家デビューした船戸氏だが実はデビュー前に外浦吾郎名義で脚本を担当、1976年の『落日の死影』ほか約30の作品を書いているのだ。船戸氏が語る。
「脚本は原稿用紙20枚ほどの短いものだけど、一切の人間性を持たないという“ゴルゴ像”を守って書く。例えばゴルゴにとって食事は車におけるガソリンと同じで、好みなどを口にしてはいけないといった具合。主人公は心情を吐露しないため、動作や第三者の視点からドラマ性を持たせ、物語を進めなくてはいけない。
しかも、俺が渡した脚本を、作者のさいとう・たかをさんはさらに削り、逆にある部分にはグッとフォーカスする。自分の脚本が作品になったのを見て、エンターテインメントとはこういうものかと思った。この経験は、後に小説を書くうえでずいぶん役に立った」
もう一つ、ゴルゴの脚本を書く上で注力しなければいけないのが、現実世界の国際情勢を鑑みることだ。連載初期は東西という明確な“二項対立”で成り立っていた冷戦構造下。そこからベルリンの壁崩壊に象徴される共産主義の崩壊、湾岸戦争、第三世界の発展と世界情勢は多様化していくが、様々な局面の中で彼の銃弾は暗躍し続けてきた。核などの大型兵器ではなく、たった一発の銃弾で時代を渡り歩いてきたのがゴルゴ。
「いわば、彼の存在は現代史への透徹した批評でもあると思う」(船戸氏)
『落日の死影』は、パラオ諸島にある毒物研究所の破壊工作を依頼されたゴルゴが現地で同じ任務を受けたもう一人のスナイパーと出会うというストーリー。今回の小説版ではハニートラップで男を翻弄する美女が新たに登場するなど、設定は現代的にアレンジされ、スケールアップしている。
船戸氏は今もなお、インターネットなどを使用することはなく、取材と資料の読み込みにより執筆を続ける。そうして生まれた小説という新たな舞台で、ゴルゴの銃口が火を噴く――。
撮影■太田真三
※週刊ポスト2011年3月11日号