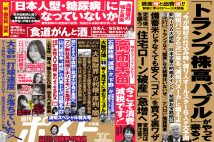日本には浮気相手、愛人とも違う「妾」という言葉があった。語源は、目をかけて世話をする、からきているとされる(妻の次という意味で「二号」ともいう)。妻もその存在を認めているのが、ただの不倫相手との大きな違いだ。「衣食住を、男性がすべて面倒をみて、その上で“お手当”を渡す関係です」(風俗史家の井上章一さん)
少なくとも江戸時代初期には、妾という存在はあったそうだ。「当時の結婚は、家を継続するためのもので、身分の高い人ほど、ある程度の身分の相手から妻を選びました。そうした身分の違いから、妾のほうも、妻になりたいと思う人はいませんでした。経済的にも援助を受けていたので、その立場を受け入れていたのでしょう」(前出・井上さん)。
古代から近世では、貴族や大名の多くが、側室(貴人の妾)を持った。ちなみに、徳川秀忠は「江」を正室にして以降、側室を持たなかったとされるが、これは珍しいケースのよう。政界では伊藤博文、田中角栄にも妾がいた。実業家にも妾を持つ人が多かったといわれる。
※女性セブン2011年4月21日号