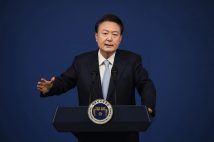ヒトの身体は、約60兆の細胞からなり個々の細胞には2万数千種の遺伝子が記録されている。2003年にヒトゲノム(遺伝子)の解読が完了し、がんは遺伝子変異によって発生すると考えられ、ゲノム解析でがんの発生・増殖のメカニズムが解明されると思われたが、説明できる疾病は予想に反し少なかった。
近年、がんの発生・増殖に関し遺伝子発現を制御するエピジェネティクスに注目が集まっている。がん治療は、がんの増殖に関わるシグナル伝達や血管新生をターゲットにした分子標的薬が臨床で利用され始めたが、新しい領域としてエピジェネティクス治療に関する研究も進んでいる。
愛知県がんセンター研究所分子腫瘍学部の近藤豊室長に話を聞いた。
「DNAにある遺伝子は、活性化して発現することで初めて働くようになります。エピジェネティクスは、遺伝子発現をオン/オフにする制御を行なっている機構です。エピジェネティクスには、主にDNAメチル化、ヒストン修飾、クロマチン構造変化、非翻訳RNAの4つが相互作用しながら、遺伝子の働きを調整していると考えられます」
例えば、一卵性双生児は一つの受精卵から2人が生まれたので、DNAの設計図は全く同じである。しかし一人はがんになり、残り一人はがんにならないケースも見られる。この場合、遺伝子以外にがんの発生に環境因子が関わっていることが考えられる。
発がんにかかわる環境因子は、「たばこ」「ある種の食品」「感染」「アルコール」が挙げられ、これらは発がん物質として遺伝子変異を起こすだけでなく、エピジェネティクスにも影響を及ぼし、がんになる。
例えば、肝炎ウイルスに感染すると最終的に肝がんになるが、感染によってエピジェネティクスの一つであるDNAメチル化が肝臓に蓄積し、複数のがん抑制遺伝子が働かないようになっていることが判明した。さらに、肝がんだけでなく、ほとんどのがん細胞でDNAメチル化異常が蓄積していることがわかった。
(取材・構成/岩城レイ子)
※週刊ポスト2012年10月26日号