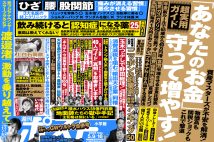2012年上期の生産台数、前年同期比19%増の255万3000台─日本の自動車メーカーとしてはトヨタ自動車に次いで2番目となる世界生産500万台の達成にいよいよ王手をかけていた日産自動車。慢性的な巨額債務に苦しみ、1999年には倒産の危機に瀕してルノーに支援を仰いだかつての悲壮感はない。今年3月期決算は、営業利益が5458億円と3期連続の増益。トヨタの3556億円を大きく上回っている。
そんな日産の「次の10年」で最大のリスクは「ポストゴーン」である。社内でもそれを不安視する声は少なくない。
後継者はいるのか。それ以前に、「次の10年」に向けてリーダーを育ててきたのか。人と金を管理するマネージャーではなく、「決断するリーダー」としての人材を育てることは容易ではない。
日産は1999年にNAC(ノミネーション・アドバイザリー・カウンシル/ナック)という組織を設け、2003年にキャリアコーチ制を始めた。
キャリアコーチは、将来のリーダーになる候補者を若い人材から発掘する役目を負う社員のこと。その数は5人ほどで、世界中の人事部と連携。開発や生産、営業といった機能別、さらに日本や米国、中国、タイなどの地域別に人材を発掘していく。世界のどこかで20代や30代前半の若手がプレゼンをする際は、“忍者”のように会場に潜入。隅の席で静かに聴いている。
キャリアコーチの眼鏡にかなうと、若手は将来を期待される「ハイポテンシャルパーソン」の候補者としてリストアップされる。この時点で本人には知らされていない。
ナックは、ゴーン社長や志賀俊之COOらエグゼクティブ・コミッティ、さらにキャリアコーチらから成る。候補者リストはナックで開示され、ゴーン社長らメンバーは1年間かけて候補者と面談する。「近くに寄ったから、話をしたい」などと、いきなりゴーン社長や志賀COOが現われる。食事をしながら、入社してからの問題意識や現在の仕事に対する改善意欲などが話題になるケースが多い。
1人の候補者に対し複数のナックメンバーが面談を行なうため、役員の来訪は相次ぐ。そして、ハイポテンシャルパーソンが選定される。
「重視される選定基準はコンピテンシー(行動特性)です。日産の行動指針、『NISSAN WAY』に則って仕事をしているかどうかなどを見ます。見かけのプレゼンのうまさや、語学の堪能さは二の次」(ナックメンバーの一人)
選ばれると、特別な育成プログラムにより、海外現地法人の社長や役員などに突然抜擢される。ある国で工場幹部となった後に、別の国で販社社長を経験させるなどする。「ただし、ハイポテンシャルパーソンに選ばれたからといって、必ず出世するわけではない。リーダーになるチャレンジの機会を与えられた形です」(別のナックメンバー)
月に1度開催される本社のナックの会議では、抜擢する人材の選定や抜擢後の動向、ポストの後継プランや育成プランなどが議論される。
志賀COOは語った。「ハイポテンシャルパーソンは、いま世界で約150人います。外国人もいますし、女性もいます。ナックとキャリアコーチ制度を10年ほどやってきたので、役員になったハイポテンシャルパーソンも多い。1人のリーダーに頼るのではなく、計画的にリーダーを育成してきた。会社全体でチャレンジしようという企業風土も醸成された。仮にゴーンが離れても、昔の日産に戻ることはありません」
1990年代までの年功序列で同質のマネージャーを大量に生んだのと異なり、真のリーダーを育成しようとしてきた。「ゴーンが去るとなれば、少なからず組織は動揺するだろう。彼と同じような、世界中に人脈があって、アップルのスティーブ・ジョブズにも通ずるような“やるといったらやるんだ”といったハッタリができるカリスマは、なかなかいない」(幹部の1人)
ゴーン社長も志賀COOも、日本企業の経営者としては若手だ。しかし、海外のグローバル企業のトップと比較すれば、50代後半は決して若くはない。自動車産業の変化のスピードを考えれば、40代のトップ起用など思い切った経営の若返りもあり得る。
欧米流でも日本的でもない、独自の人事システム、人材育成を日産は推進してきた。その成果が試されるのが、恐らくは「ゴーン退任」を経験するこれから始まる10年である。
※SAPIO2012年12月号