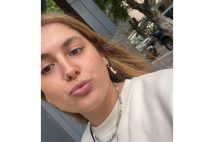里親と里子との心温まるエピソードをつむいだ1冊の本が話題を呼んでいる。昨年9月に発行された『まいにちの家庭レシピ 里親ファミリーの日常風景』(NPO法人キーアセット)。わずか43ページの小冊子にはこんな想いが込められている。
「里親は裕福でも地元の名士でもなく、普通のおじちゃん、おばちゃんたちです。私たちにとって当たり前の日常が、里子には特別な体験になる。“食”を通じて、里親家庭の温かさを伝えたかった」
と発行者の渡邉守さん(43才)。ここで紹介するのは普通の家庭で起こった、ささやかな物語――。
上杉美代子さん(仮名・67才)が里親になったきっかけは33年前、近所の子供を預かっていた時に、その母親がそのまま逃げてしまったことだった。
「当時、うちには小学生の娘が2人いましたが、預かったその子はまだ生後10か月でした。あまりにもかわいそうで、市に相談してその子の里親になることを決めました。今までに14人の子を預かってきました」(上杉さん)
上杉さんは虐待された経験などのある児童を養育する「専門里親」(※)の資格を取得しているため、心に深い傷をもつ子供を預かることが多い。
そうした子供たちと暮らすなかで、上杉さんの頭を悩ませた問題が食生活だった。
児童養護施設での生活が長かったある少年は食が細く、料理を毎回残していた。
上杉さんが「全部食べなきゃダメよ」と注意すると、その少年は上杉さんに気づかれないように食べ残しをゴミ箱に捨てるようになった。上杉さんはご飯を食べる楽しみを知ってもらいたいと、毎日メニューを替えては、料理を作り続けた。
そんな少年がある日、残さず食べた料理があった。ヒレカツだ。特別に工夫をしたわけではない。普通の家庭で食べるヒレカツだった。
「『施設でこんなうまいカツ、食べさせてもらったことがない。おばちゃん、カツってお菓子みたいにやわらかいねんな』って喜んで。最後には『おばちゃん、お風呂あがってから、もう少しもらってええかな』って言って、ひと風呂浴びたあとにテレビを見ながらつまんでくれました」
食事のあとは、「食べられない時はラップをかけて残しておいてね」という言いつけを守るなど、里子たちは少しずつ、新しい習慣を身につけていった。
※専門里親 虐待された経験のある児童や非行などの問題を有する児童などを養育する里親。一般的な養育里親の経験が3年以上、おおむね3か月以上の研修が必要などの条件がある。専門里親に委託できる児童の数は一度に2人まで、委託期間は2年(必要に応じて延長あり)。
※女性セブン2014年7月10日号