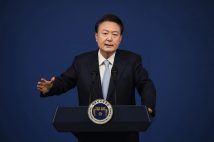【著者に訊け】堀川惠子/『原爆供養塔 忘れられた遺骨の70年』/文藝春秋/1890円
広島に住む人でもその存在を知らない人が多い「原爆供養塔」。そこにはおよそ7万人が遺骨として眠っている。佐伯敏子さんはいつもその前にいて、遺骨を遺族のもとに届けていた。2013年の春、著者・堀川さんは、年を重ね、今は老人保健施設で過ごす彼女を訪ねる。そして原爆供養塔にまつわる取材が始まる。遺骨となった死者たちの人生、遺族の戦後、70年の日本と広島の歩み…封印された供養塔がさまざまな事実を呼び起こしていく。
広島平和記念公園の中にひっそりとある、何の説明書きもない小さな塚。本書の題名の「原爆供養塔」は、引き取り手のわからない原爆の犠牲者の供養のため、1955年につくられたものだ。地下には七万柱もの遺骨が納められているが、一方で氏名が判明していながら、遺族のもとに戻っていない遺骨が今も815名分ある。広島市はその名簿を毎年7月に公開してきた。
「見れば番地や勤め先までわかっている人もいる。それなのに、どうして無縁仏のままになっているのかがずっと気になっていたんです」
本書でこの謎に迫った堀川子さんは広島生まれ。2004年、地元テレビ局を退社して東京に来てからは、『死刑の基準』『教誨師』などの著作で高く評価されるジャーナリストだ。その彼女にとって原爆供養塔をめぐる取材は、故郷広島の知られざる戦後史をひもとく途方もない作業となった。
本書の主人公に佐伯敏子さんという現在95才の女性がいる。原爆で家族の多くを失い、自らも原爆症に苦しんできた彼女は、あるときから供養塔に日参し始め、いずれ遺骨を遺族のもとへ返す日々を送るようになった。堀川さんは病に倒れた彼女の意志を継ぎ、遺族を探そうとするのだが――。
「何人かはわかるだろうと最初は思っていたし、お会いできれば喜んでもらえると考えていました。ところが取材を進めるうち、全く違う現実に向き合うことになったんです」
まず遺族が見つからない。番地や名前が存在しないこともあれば、すでに遺骨は帰ってきていると話す遺族、中には生きていたという人もいた。
「そのうちに気づいたんです」と堀川さんは言う。「これは単なる人探しじゃないんだ、って」。
戦後70年――遠く彼方になりつつある「ヒロシマ」の光景や人々の思いに、自分はどう向き合うべきか。それが問われていた。そんななか、彼女は遺骨をたどった先で出会った、戦争をめぐる個々の物語に耳を傾けていくことになる。それは佐伯さんというひとりの女性が、なぜ人生をかけて遺骨の遺族を探し続けてきたのかを考える旅でもあった。
「取材の途中で弱音をはいたとき、病床の佐伯さんにこう言われました。“あんた、何を言いよるんね。死者は自分で歩けんのんよ。知ったもんがやらんといけんじゃろう…”遺骨をたどった先で多くの戦争の記憶に触れていると、それが決して昔話ではないことを実感します。記者になって四半世紀。私はこの本を書くことで、ようやく自分が広島と向き合い始めたのだと感じています」
知った者の責任――佐伯さんの言葉に導かれながら、彼女は今も遺族を探す旅を続けている。
(取材・文/稲泉連)
※女性セブン2015年7月9・16日号