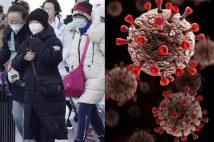朝日新聞の読者投稿欄「声」に掲載された66歳男性の投稿が論争を呼んでいる。
「タレントを含めて若い人が、妻を『嫁』と言うことに違和感を感じる。40年ほど前に結婚した私たちは『嫁』や『主人』という言葉は使うまいと決めた。戦前の『家制度』を思い起こすからだ。現憲法では結婚は個人と個人のものであり、女性が他家に嫁ぐことではない」
要するに第三者の前で自分の妻をどう呼ぶべきか、という話なのだが、これが同欄で“大論争”に発展、インターネット上にも飛び火し、ちょっとした騒ぎになっている。
嫁という言葉は江戸時代からあったが、単に「息子の妻」や「新婚の女性」という意味だったという。
家族法制に詳しい近藤佳代子・宮城教育大学教授によると、「家に入る」という意味が強調されて使われるようになったのは明治31(1898)年の民法施行から。以後、「家に入った女」という意味で自分の息子の妻を「嫁」と呼ぶことが定着していったが、戦後、家制度が廃止されると、「夫個人と結婚したわけであって夫の家に入ったわけではない」という意見が増え、嫁という呼び名は敬遠されるようになっていった。
それが近年、自分の妻を指して「嫁」という呼び名が復活してきた背景には、大阪文化というよりは大阪の芸人文化の影響が大きいという。大阪の芸人たちが使う「うちの嫁」という言い方が、若い世代に浸透していったのだ。
実際、調査データを基にした記事を配信するサイト・しらべぇがアンケート調査で「家庭外で『妻』について話す際に好感が持てる呼び方はどれですか?」と世代別男女に聞いたところ、世代によって全く違う結果が出た(6月15日配信記事より)。60代以上は「かみさん」が1位、以下、50代は「家内」、30~40代は「奥さん」、20代は「妻」、そして10代以下の世代ではついに「嫁」が1位という結果になった。
若い世代は、朝日新聞への投稿にあったような「家制度」など全く意識せず、「嫁」が定着しつつあることがはっきりと表われている。
では、なぜ関西では「嫁」という言い方がスタンダードになったのか。上方落語の月亭可朝師匠(77)が解説する。
「楽屋で芸人同士が話す際に『家内』や『妻』というのは少し堅い。そこで、東京の落語家が使う『うちのカミさん』という言い方に対して、さらに親しみやすい言い方として関西では『うちの嫁はん』という言い方を昔からしていたんです。
噺のなかでは『かかあ』といいますが、楽屋なんかではみんな『嫁はん』といっていた。いまの若い芸人たちは、その『嫁はん』を略して『嫁』というようになったんちゃいますかな」
※週刊ポスト2015年7月31日号