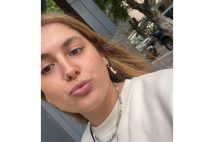61才女性の衝撃告白手記【後編】
性に奔放な母親に嫌悪感を抱いていたのに、自分もまた同じ道を歩んでいた──。小野美佐江さん(静岡県・61才)が、数奇な運命を語る。
〈本稿は、「自らの半生を見つめ直し、それを書き記すことによって俯瞰して、自らの不幸を乗り越える一助としたい」という一般のかたから寄せられた手記を、原文にできる限り忠実に再現いたしました〉
【前回までのあらすじ】
東京郊外で、2DKの団地住まい。幼い頃から毎晩、ふすま1枚隔てた部屋から聞こえてくる母のあえぎ声に耳をふさいでいた私もまた、いつしかセックスのとりこに。高卒後、東京で就職した時は、嫌いな男の子供を身ごもっていた。
* * *
「あなた、妊娠していない?」。朝、寮の洗面所で顔を洗っているときのこと。
「あはは。よく言うわ~」と覚えたばかりの都会語で先輩に返すと、「おかしいなぁ。私、妊婦は見るとわかるんだけどな」と首を傾げられました。
実は生理がなくなって3か月がたっていました。思い当たる男は、就職前に気まぐれで寝た1人だけ。その男が、働いている駅ビルにやってきては、「帰りは何時だ?」とつきまといます。
中2の初体験から、男を「好き」と思ってセックスをしたことはなかったけど、この男は別。歯の黄色さもにおいも、服装のセンスも、何もかも嫌いでした。嫌いすぎて顔を見るだけで吐き気がします。
つわりでした。だけど妊娠を認めたら仕事も住まいも失ってしまう。当時の私はそんなことばかり考えていました。
「ほら、あの子よ」
「本人は違うと言っているんだけどね」
仲よくなった同世代の先輩や同僚が、目くばせして私の噂話をするようになるまで、そう時間はかかりません。私のお腹は前に張り出し、どう見ても妊婦でした。
◆力強く初乳を飲むわが子に、パニックを起こした
妊娠6か月。もしあの時、中絶をしていれば、私の人生はどうなっていたのか。お金のない私はそうしたくてもできません。とうとう男に話しました。「結婚しよう」と男は言いましたが、私は中絶する費用が欲しい。話は平行線です。どうにもならなくなっていたところに、私の母親が出てきました。
「後のことは私が引き受けるから、産みなさい」
いつも「お父さんが」としか言わなかった母親がやけにキッパリしています。
「私は結婚もしないし、子供も育てられない」と言うと、「それでいい」と。そこまで言われたらあれこれ考えるのも面倒になり、母親の言うとおりにすることにしました。
仕事を辞めて、男とも別れ、母の姉の家で臨月まで過ごし、産院で出産したのです。今となればこのときの記憶は何もかもぼんやりしていますが、1つだけ忘れられないことがあります。