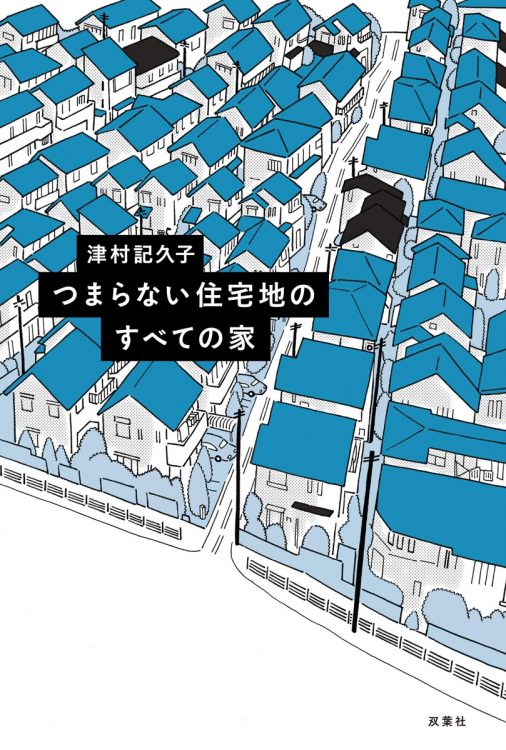『つまらない住宅地のすべての家』著・津村記久子
【書評】『つまらない住宅地のすべての家』/津村記久子・著/双葉社/1760円
【評者】鴻巣友季子(翻訳家)
私は集合住宅を舞台にした群像劇小説が好きだ。とくにドラマチックなことや事件が起きるわけではなく、普通の人びとの日常がこまごまと描かれる。近年では、長嶋有の『三の隣は五号室』や、柴崎友香の『千の扉』などなど。
『つまらない住宅地のすべての家』は集合住宅ではないが、町のある一画に並ぶ家十軒の住人たちの数日間を主に描く。ただし、事件は起きる。横領犯の女が脱獄し、民家から盗んだ服に着替え、この界隈に逃げてきているらしいのだ。
近所の治安を守るために、はりきって交替の見張り体制を組む男性がいる。中三の息子と二人暮らしなのは、妻が出ていってしまったからだ。逃亡犯に「わたしも連れていってくれないかな」と呟く小学生もいる。父は不在、母は家事育児をろくにしないので、さらに幼い妹を抱え、一家のヤングケアラーになっているのだ。
平和そうな住宅にも凶悪犯罪の芽はある。可愛い女児を誘拐しようと狙っている若い男もいる。あるいは、わが子をどこかに閉じこめる計画を進めている父母もいる。ご近所さんの学歴、子どもの数、家の大きさ、職業をめぐって、妬みが、意地がある、微妙なマウンティングがある。鬱憤がたまる。
十軒の暮らしが描かれるうちに、幾人かは逃亡犯との意外なつながりを持つことが明らかになる。彼女がそもそも横領に手を染めたのは、ある堪え切れない怒りを抱えていたからだった。
一方、この住宅地の人びとも、「社会から押し付けられている不全感の解消」のために犯罪に走ろうとしたり、なにかを忘れるために凝った料理を作って自己肯定感を得たり、なにかを守ろうとしてなにかを壊したりして、迷走しているのだ。
逃亡犯が入りこんできたことから巻き起こる小さな波乱。つまらない住宅地に起きたつまらない事件は、ゆるやかな連携を呼びこみ、驚きの大団円を迎える。本当に面白い小説とはこういうものだと実感する傑作だ。
※週刊ポスト2021年8月20日号