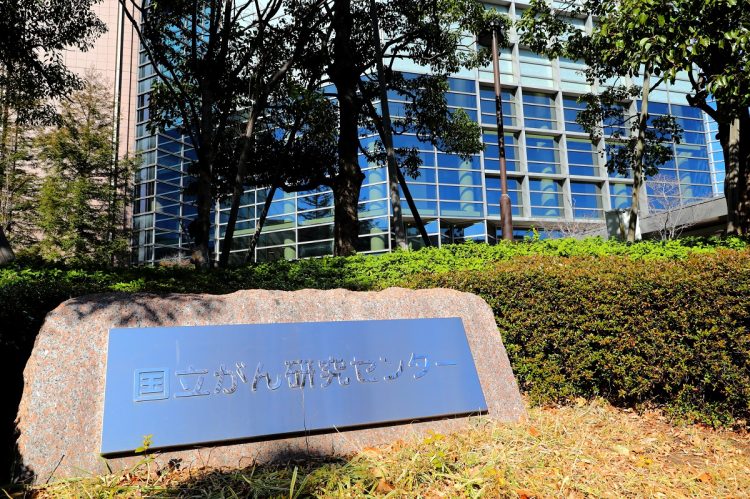がんと診断された患者の「5年生存率」と「10年生存率」を公表(写真/アフロ)
いまや、日本人の2人に1人が罹るとされるがんが「国民病」と呼ばれ始めたのは、約40年前のこと。暮らしの変化や、医療の進化とともに、私たちとがんとの関係は絶えず変貌している。最新データが導き出した、「日本人とがん」の現在、未来とは──。
国立がん研究センターが今年3月、がんと診断された患者の「5年生存率」と「10年生存率」を公表した。全国のがん診療連携拠点病院などが参加する「院内がん登録」の大規模データを集計したもので、2010年にがんと診断された患者約34万人の10年生存率は、53.3%、2014〜2015年にがんと診断された患者約94万人の5年生存率は66.2%だった。がんになった人の半数以上が“がんを乗り越えた”もしくは“がんと共存”していることになる。
がん患者の生存率が高まった大きな理由は薬の進歩もあるが、もうひとつの理由として、「早期発見」がある。がんを早く見つければ治療も早くにできるため、がんの働きを抑制したり、転移も未然に防げるケースも多く完治の見込みも高くなる。国立がん研究センターの調査でも、多くのがんで「ステージI」の生存率は高くなっており、ステージIとステージIVとの生存率には大きな開きがある。
早期発見を謳ったがん検診にもさまざまなものがあるが、厚労省が推奨するのは、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんの5つの検診だ。とりわけその正確性が注目されているのが消化器系の内視鏡検査だという。医療経済ジャーナリストの室井一辰さんが言う。
「ここ10年くらいの研究で、内視鏡検査によって生存率が高まることが確認されました。胃がんや大腸がん、食道がんなどについては、内視鏡によって早めに見つける動きが広がっています」(室井さん・以下同)
すなわち、生存率が低いがんほど、早期発見が難しいといえるということだ。
「すい臓がんや胆嚢がん、肝臓がんなどはほかのがんに比べて生存率が低く、その要因はひとえに発見の難しさにあります。これらはさまざまな臓器の裏側にあり、検査自体が難しい。また、ほかのがんに比べて初期に痛みなど自覚症状が出にくい。いくつもの臓器と接しているため、早い段階で転移しやすいことも治療を難しくしています」
このとおり、早期発見の大切さについては、いまや誰もが認知するところだ。しかし、一方で専門家たちは「やみくもに検査をする必要はない」と声を揃える。内科医の名取宏さんが言う。