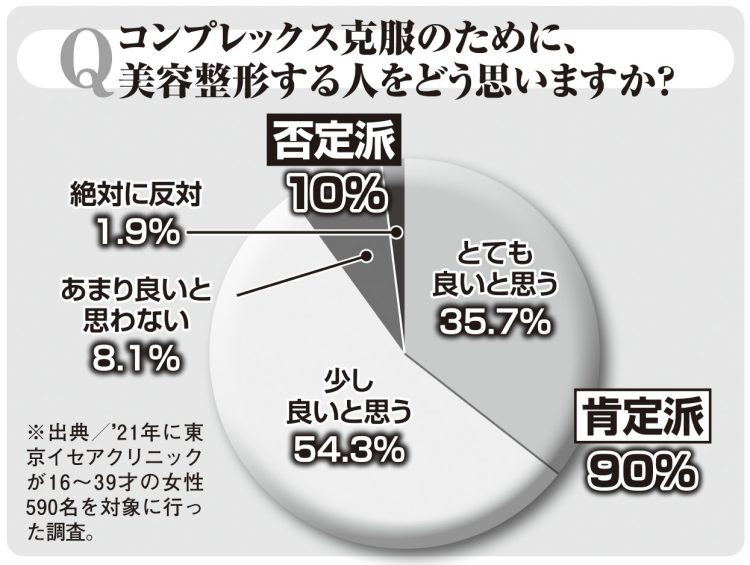肯定派、否定派の割合は?
技術が発達してくれば、次に生まれるのは「美しくなりたい」という純粋な欲望だ。だが、欧米ではキリスト教的観点から「健康な体にメスを入れることは神への冒涜だ」という考え方がスタンダードであり、美しさのため“だけ”に外科手術を行うことは異端とされてきた。それを覆したのが精神科医のアルフレッド・アドラーだった。日本美容外科学会理事長で北里大学医学部形成外科・美容外科学主任教授の武田啓さんが解説する。
「アドラーは“コンプレックスは病気”だと提唱しました。その考えが広まることにより、外見の悩みは『病巣』であり、メスで取り去り、治すことは立派な医療だということが認められたのです」
以降、海外における美容整形は飛躍的に発展していく。しかし先駆けだったはずの日本では、なかなか一般化しなかった。その背景について海野さんは「まず『親からもらった体にメスを入れるなんて』と否定する考えが強く、外見へのこだわりに対しては“心を磨け”といさめられることが多かったようです」と指摘する。
「また、医療とは病気やけがを治すものであり、外見の美にかかわる施術は邪道であり、それを行う医者はまっとうではないと医学界でも言われていたそうです。加えて、1980年代まで見た目の医療は外科手術しかなかったため、患者さんは見た目が仕事に大きく影響する芸能人や“水商売”と呼ばれていた人がほとんど。一般人にとっては“世界が違う”という感覚でした」(海野さん)
事実、日本初の二重まぶたの整形手術が行われたのは1896(明治29)年と古いが、その際、施術を受けた16才の女子学生は、そのことが理由で当時通っていた学習院を除籍になった。そうした「美容整形はいかがわしい」という感覚は大正、昭和から平成に入っても日本人につきまとい続けた。美容整形外科医として現場に立ち、27年になるというアテナクリニック銀座本院の定村浩司総院長は、当時の様子をこう話す。
「ぼくが美容整形外科医になった1996年、この分野を牽引していたのは『美容整形は富と余裕の象徴』という風潮のあったアメリカであり、日本はまだまったくそこに追いついていないというのが同業者たちの間の共通の見解でした。
2001年から放送が開始されたバラエティー番組『B.C.ビューティー・コロシアム』(フジテレビ系)によって美容整形の認知度自体は上がったものの、一般人が容姿の悩みを番組内でジャッジされ、整形を施されるという内容。『整形をする子って、やっぱり普通じゃないんだ』という偏見をベースにした、キワモノ的な取り上げ方だと憤慨している医師が多かったことを覚えています」