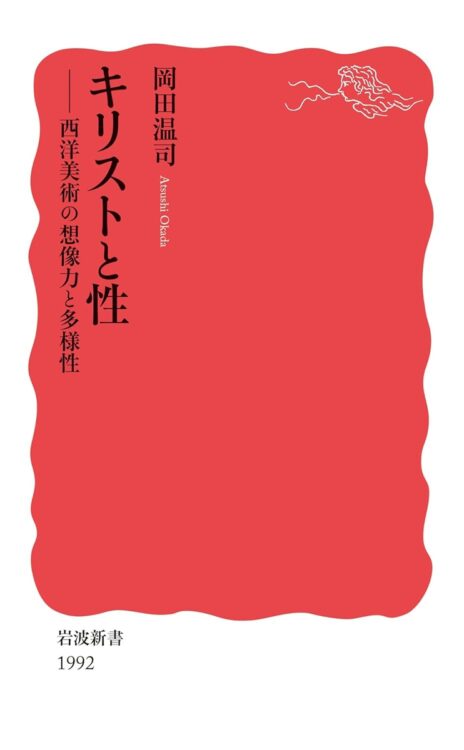『キリストと性 西洋美術の想像力と多様性』/岡田温司・著
【書評】『キリストと性 西洋美術の想像力と多様性』/岡田温司・著/岩波新書/1122円
【評者】井上章一(国際日本文化研究センター所長)
イエス・キリストは、ゴルゴタの丘で十字架にかけられた。そのさい、脇腹を槍でつかれている。復活後も、傷口はふさがらない。そこからエクレジア、つまり教会は生まれたとするイメージが、中世には流布された。
それだけではない。キリストが教会の母胎なら、その傷口は産道の出口、つまり女性器となる。そして、そこを女陰としてえがく絵画も、数多くでまわった。傷をうつした布が、下品な言い方だけれども、まん拓のように描写された絵は少なくない。
使徒のひとりであるトマスは、イエスの復活をあやしんだ。真偽をたしかめたくて、その傷口に自分の指をさしいれている。カラヴァッジョがその場面を絵画にした。これも、傷口が女陰として描出された伝統を知ってながめると、印象はちがってくる。
キリストと使徒ヨハネには、どこか同性愛じみた気配がただよう。そこをえがいたとおぼしき絵は、けっこうある。『ヨハネによる福音書』じたいが、イエスによせる彼の想いをしるしている。
いや、うらぎり者とされたユダにだって、そういう気持ちがなかったわけではない。ユダとイエスの接吻は、ながらく美術のテーマになってきた。そして、そこにゲイ的な雰囲気をそえた作品も、まま見かける。
日本人は、クリスチャンと聞けば、まじめな人を思いうかべやすい。近代日本がキリスト教を、禁欲の宗教としてうけとめたせいだろう。しかし、この宗教は、根っ子にセクシュアルな部分をもっている。あるいは、クイア、LGBTQのQにあたる感性も、ともなっていた。この本は、そこをほりおこし、読者に提示してくれる。
今につづくおりめただしい教会は、かくしてきた。異端の烙印をおしてもいる。いっぽう、美術家たちは、しばしばそういうところに興味をいだき、えがいてきた。そして、それらは作品として今につたえられている。これは、美術史の大家があらわした、異色のキリスト教美術史である。
※週刊ポスト2024年2月9・16日号