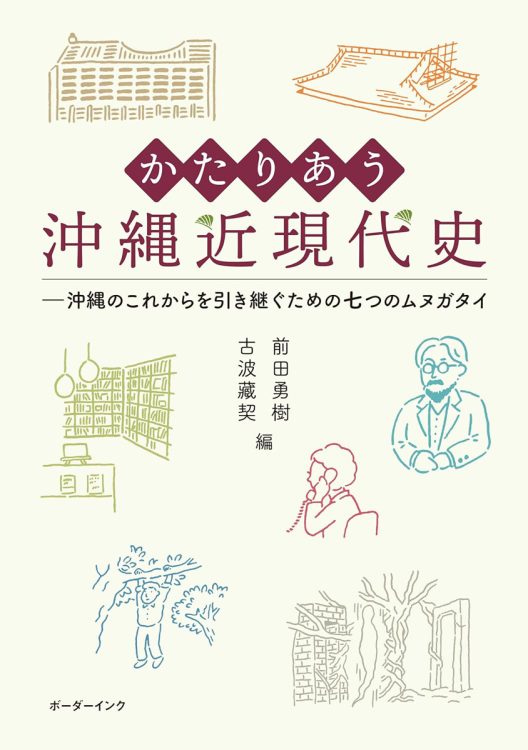『かたりあう沖縄近現代史─沖縄のこれからを引き継ぐための七つのムヌガタイ』(前田勇樹、古波藏契・編/ボーダーインク/2025年1月刊)
今年は、昭和元年から数えてちょうど100年の節目。つまり「昭和100年」にあたる。戦争と敗戦、そして奇跡の高度経済成長へと、「昭和」はまさに激動の時代であった。『週刊ポスト』書評欄の選者が推す、節目の年に読みたい1冊、読むべき1冊とは?
ノンフィクション作家の与那原恵氏が取り上げたのは、『かたりあう沖縄近現代史─沖縄のこれからを引き継ぐための七つのムヌガタイ』(前田勇樹、古波藏契・編/ボーダーインク/2640円 2025年1月刊)だ。
* * *
一九二五年を沖縄の立場から見れば、琉球王国が日本に併合されて四十六年しか経っていない。今から四十六年前の七九年といえば、インベーダーゲームのピークの年で、鮮明に記憶する人も多い過去だろう。昭和百年というけれど、沖縄はその四分の一以上、二十七年間が米軍施政下にあった。
沖縄戦の記憶も生々しい五〇年、朝鮮戦争が勃発。日本は特需景気に沸いたが、米政府は東アジア情勢を警戒し、沖縄を半永久的に支配するとともに恒久的な基地建設を推進する方針を示した。土地の強制接収が相次ぎ、沖縄住民は激しく抵抗。その沈静化を目論んだ米側は経済的向上を企図し、五八年に法定通貨をそれまでのB円(米軍発行の軍票)からドルに切り替え、本土復帰(七二年)まで使用された。沖縄の百年は日本に組み込まれる一方、米国も絡んだ複雑な歴史を刻み、現在もその延長線上にある。
しかし、沖縄は虐げられた存在としてのみ生きてきたわけではない。〈復帰を境に「日本のなかの沖縄」というそれまでの枠組みが見直され、各分野において「沖縄とは何か」という真剣な問いが追及された〉。なかでも歴史研究においては、八〇~九〇年代が大きなターニングポイントとなり、新たな書き手が続々と登場した。
彼らは米軍施政時代を生きた世代だ。いわゆる「沖縄学」が琉球王国崩壊を当人、もしくは父母が体験した世代によって創始されたように、複雑な時代状況ゆえに琉球・沖縄を深く見つめていた。
本書は若手・中堅研究者が〈先輩方〉の研究者らと世代を超えた対話を重ね〈思想的水脈〉を掘り起こす試みである。琉球・沖縄史、民衆史、教育、メディア、経済、女性史など、テーマは多岐にわたり、沖縄近現代をめぐる意義深い議論を展開。未解決の問題、世代間の断絶にも焦点を当てた。
研究活動とは、会うこともなかった先人から、未来に生まれる世代まで含めた〈チームで取り組む共同作業〉だといい、琉球・沖縄とは何かを問いつづけている。
※週刊ポスト2025年4月18・25日号