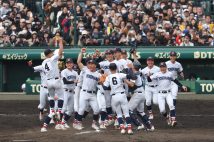金価格の低迷が続いている。1トロイオンス(約31グラム)当たり1200ドル前後の相場となっている。そこから金価格はどのような動きをみせるのか、金の動向に詳しい豊島逸夫氏が解説する。
* * *
金価格の動向を巡って今年前半、欧米市場に大きな変化が見られた。それまで続いてきたドル高傾向がドル安へと一転、長期金利も上昇に転じている。
カギを握るのが、ヘッジファンドの動向だ。今年3月に始まったECB(欧州中央銀行)の量的緩和を見越して、ヘッジファンドをはじめ投機筋がユーロ売り、欧州国債買いに走ったが、さすがにやりすぎたのだろう。ドイツ国債の利回りがマイナスも視野に入り、スペイン国債の利回りが米国債をも下回るような異常事態が一気に巻き戻され、金利は上昇、ユーロ高に伴うドル安という流れに一変した。
加えて「Sell in May(5月は売り)」という米国の相場格言通り、NYダウやドイツDAX指数なども下げが目立つようになった。
本来、「有事の金」といわれるように、「ドル安」「株安」は金価格にとって追い風となるはずだ。しかし、目下のところ、金の人気は高まらず、国際金価格は1トロイオンス当たり1200ドルを割り込む展開が続いている。
おそらくこの傾向は今年後半も続くに違いない。最大のポイントは3つある。
まず1つ目が「米国の利上げ」だ。米国の今年3月の貿易赤字が1996年以来の増加率で大幅に拡大し、マイナス成長も予測されるなど米国経済の悪化懸念が高まるなか、当初は今年半ばとも見られていた利上げの時期が後ズレする公算が高まっている。
ここにきて「9月説」どころか、「12月説」まで浮上しているほどだ。金利を生まない金はドル金利の上昇が“天敵”であり、その時期が先送りされることは本来、好材料である。しかし、実際には、いつ金利が上がるかわからないという利上げ懸念が世界的な金の購買意欲を削ぎ落としているのだ。この利上げ圧力が今年後半も続くのは必至だろう。