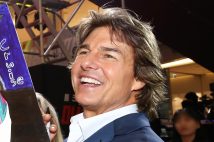『空気を吸う、道を歩くだけでいいんです。空気の味から、足の裏から家康が分かるかもしれない』と。寺に一歩入ったら全く俗界と違う。静寂の世界で空気が澄んでいました。
竹千代(※少年時代の家康の呼称)の間の隣の一部屋を空けていただき生活をしたのですが、それでも家康は見えてこない。
寺から逃げようかと思って庭掃除を終えると、玄関に倉内松堂老師という禅師が初めて姿をお見せになられました。『朝から晩までお部屋の電気がついていますが、お勉強は進みましたか?』とニコニコしながら聞いてくださる。『考えれば考えるほど分からなくなって、本当にどこかへ消えてしまおうと思っています』と正直に答えたら、老師が庵に招いて煎茶を淹れてくださったんです。
一杯目の一滴は甘かった。二杯目は渋い。三杯目は苦い。『随分と味が変わりましたね』と申し上げたら『甘い、渋い、苦い。甘渋苦の三つが揃って人生の味わいなんです』とおっしゃる。
その時に思いました。家康の人生には甘も渋もない。苦の極みの連続です。それを超えて彼は戦国を終わらせた。常人では耐えられない艱難辛苦を耐えた。それは客観的にはかっこ悪いけど、我慢して一つ一つ超えて、最終的に不幸な時代を終わらせた。その凄さが家康なんだ。格好悪くて何が悪いんだ──。そのことに気づいたんです。
他の武将には私欲がある。欲望成就のための戦いです。でも、家康は違う。この不幸な時代を終わらせるにはどうすればいいかを考えてきたんですよ」
●春日太一(かすが・たいち)/1977年、東京都生まれ。映画史・時代劇研究家。著書に『天才 勝新太郎』(文春新書)、『仲代達矢が語る日本映画黄金時代』(PHP新書)、『あかんやつら~東映京都撮影所血風録』(文芸春秋刊)ほか。最新刊『なぜ時代劇は滅びるのか』(新潮新書)も発売中。
※週刊ポスト2014年10月10日号