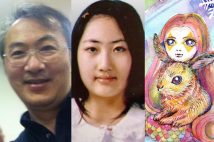何かと舌禍騒動を起こし、挙句の果てには会長就任まで「NHKのことを何も知らなかった」と発言したNHKの籾井勝人会長について、会長を任命し監督する経営委員会はどう見ているのか。2月まで委員長代行を務めた上村達男・早稲田大教授が、籾井問題の核心に迫った。
* * *
NHK会長は、およそ近代国家ではあり得ないほどの独裁的地位に陥りやすい構造となっている。今回、“変な人”が会長についたことによって、この問題が顕在化した。
籾井会長については、議論ができないという点が問題だと感じている。例えば、国会では紙を読むだけ。質問に対して、一字一句をそのまま読むだけ。そして、それでは済まない場合には、民主党との会合のように、怒鳴り出す。
周りを敵と味方に分類し、敵の主張はあくまで無視する。議論ができないことが、経営委員会でも揉める原因となった。だが、経営委員会には籾井会長を止める力がなかった。
企業を例にとれば、私が務めていた経営委員会は社外取締役で、会長に副会長・理事を加えた理事会が取締役会に相当する。
本来は取締役会である理事会が、トップである会長の独断を制限する立場にあるはずだが、実際には理事会は単なる審議機関に過ぎず、会長はその判断を、極端に言えば無視することも可能。理事会の判断に従う必要がない。
そこで経営委員会が必要になるわけだが、通常の社外取締役が他企業の経営者など経営に関する専門性を有する人が担うのに対し、NHKの経営委員のほとんどは、そうした専門性を持っていない。しかも経営委員会には、ほとんど情報が入らない。
そのため、こんなことも起きた。理事の任命は、経営委員会の同意を得た上で、会長が任命することとなっており、昨年4月22日の経営委員会で、籾井会長は理事の再任と新任を求めてきた。
ところがその際、どの理事が何を担当するかを明らかにしなかった。私はそのとき、委員長代行を務めており、その点を尋ねたが、籾井会長は、各理事の担当は会長が決めることなので、経営委員会に知らせる必要はないと述べた。