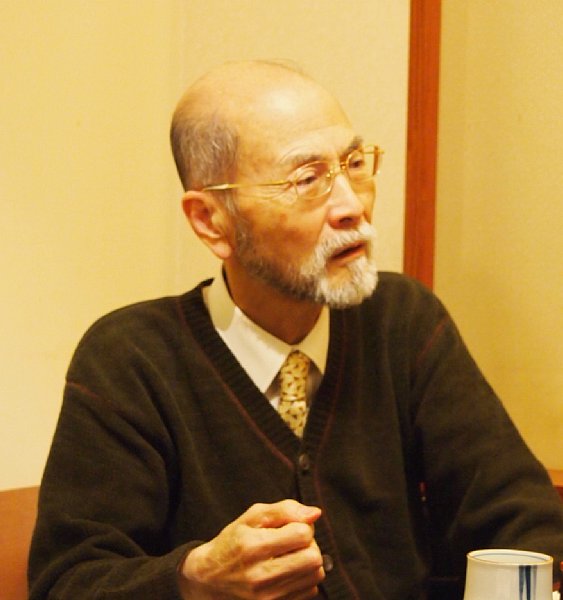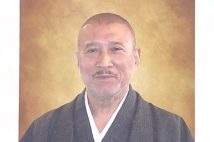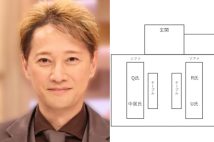評論家の呉智英氏
5月3日の憲法記念日にあわせて発表された世論調査の結果によると、いま、憲法への関心が高まり、議論するべき課題だと感じている人が増えているという。関心は高まっているようにも見えるが、評論家の呉智英氏が、現在の憲法論議がなぜ空虚なものばかりなのかについて解説する。
* * *
3月22日、政府は閣議で鈴木貴子議員の質問主意書に答えて、共産党は暴力革命の方針を変更していないとの認識を示した。
ちょっと見直した、共産党を。私はこの半世紀ほど共産党は暴力革命を未来永劫やめてしまったものと思っていたからだ。折しも憲法記念日をはさんで憲法論議の啓発記事が保革を問わず新聞に掲載されているが、どれも意図的に本質論を隠している。
憲法は国の最高法規であり、刑法、民法など全法律は憲法に従っている。しかし、唯一例外がある。条約である。刑法や民法に憲法違反の条項があれば無効であり改正が進められるが、条約はたとえ憲法に違反していても無効にはできない。条約は二つ以上の異なる統治権力(国家)間で合意した法律であるから、片方が勝手に無効にすれば国際的信用をなくす。最悪、戦争にもなるだろう。
要するに、立憲主義は統治権力内部にしか向かわない。こんなことは憲法学の常識である。
1959年、最高裁は砂川事件上告審で、争点の一つになっていた日米安保条約の合憲性について「高度な統治行為」であるから司法は審査できないとした。当然である。砂川闘争が是であろうと非であろうと、憲法論としてはそうなる。だいたい、砂川闘争は憲法に認めてもらおうとして起こした運動ではないはずだ。
それでは「統治行為論」は保守側に有利な理論かと言えば、そうではない。