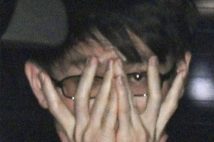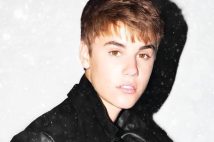牛舎で牛を飼育する江頭さん
「攻めの農業」──安倍政権が掲げる農業改革のスローガンである。日本の農業は曲がり角を迎えている。2016年の農業就業人口は200万人を切り、平均年齢は66歳を上回る。耕作放棄地は25年間で倍増し、その面積は富山県に匹敵する。
戦後ずっと続いてきた農業保護政策の破綻はもはや明らかであり、農業の在り方自体が変わらなければ未来はない。しかし、その方針を唱えても、実際に動くのは現場で農作物を生産する農家である。改革の鍵を握るのは「笛を吹く者」ではなく、実際に「躍る(生産する)者」なのである。
日本の農業には、改革を担う力があるのか。その現場をジャーナリストの竹中明洋氏がレポートする。
* * *
和牛のトップブランド「佐賀牛」の産地である佐賀県は、全国的には無名だった牛肉を、大々的な宣伝や積極的な海外輸出で、神戸牛や松阪牛に並ぶブランドに成長させた。柔らかい赤身にきめ細かなサシが入った肉は、“艶さし”と呼ばれ、さらりとした脂身の甘みとコクのある味わいが特徴だ。
鍋島藩の城下町・佐賀市の中心にあるJA直営レストラン「季楽本店」には、佐賀牛を使ったステーキやせいろ蒸しがメニューに並ぶ。店内で気づくのは、外国人客の多さだ。来店客の4分の1は香港からの旅行客で、月に1000人ほどに上る。
これは佐賀牛の海外輸出に力を入れてきた成果だという。
佐賀県東部のみやき町の畜産農家・江頭豊さん(63)は、1980年代から佐賀牛の飼育に取り組んできた。“艶さし”は、江頭さんら若手畜産農家が、和牛の血統に関する緻密なデータを集め、飼料や飼育環境の研究を重ねた成果だ。
しかし、販売スタート当初は“惨敗”だった。主な出荷先の大阪では「誰も知らない佐賀牛なんてラベルを貼っていたら売れない」と剥がされたこともあったという。