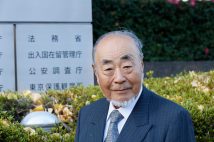『黒澤明の羅生門 フィルムに籠めた告白と鎮魂』/ポール・アンドラ・著
【書評】『黒澤明の羅生門 フィルムに籠めた告白と鎮魂』/ポール・アンドラ・著/北村匡平・訳/新潮社/2500円+税
【評者】平山周吉(雑文家)
「敗戦国を覆っていた恥辱の障壁を打ち破」る報道が日本にもたらされたのは昭和二十六年(一九五一)九月だった、と本書『黒澤明の羅生門』はオープニングに記している。映画『羅生門』のヴェネチアでのグランプリ受賞である。吉田茂首相がサンフランシスコで講和条約を締結した直後、「独立」への胎動を告げるビッグ・ニュースとなった。
「世界のクロサワ」の出発点となった名画を読み解く著者ポール・アンドラは、コロンビア大学の日本文学教授として、有島武郎、小林秀雄などを研究してきた。シェイクスピア、ドストエフスキー、芥川龍之介に挑んできた「永遠の文学青年」でもある黒澤監督を、本書は日本文学の伝統の中に位置づける。映画と文学という二つの領域をまたぎ、近代文化史の拡がりの中で映像を凝視する。
黒澤のモノクロ映像の中から、著者は「消失した都市、喪失した兄、そして黒澤の象徴的映画に潜む声」(本書の原題のサブタイトル)を取り出してくる。シナリオにも絵コンテにも描かれないが、そこには黒澤に最も大きな影響を与えた四歳上の兄がいつも写り込んでいると指摘する。
黒澤にサイレント映画とロシア文学の魅力を教えた兄・丙午は、須田貞明と名乗る無声映画の人気弁士だった。二十七歳で自殺(心中)した兄をよく知る徳川夢声は黒澤に向かって、「君は、兄さんとそっくりだな。でも、兄さんはネガで君はポジだね」と言った。