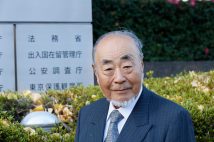弟子の立川談春(左)と立川志らく(撮影/井上たろう)
生涯にわたって年末の定番『芝浜』に向き合い続けた立川談志(享年75)。若い頃から「古典落語だけでは落語が滅びる」との考えを持っていた談志が、大晦日の情景と夫婦の愛情を描いた古典に執着したのはなぜなのか。2007年12月18日、談志が独演会で披露した『芝浜』は、「伝説の一席」と語り継がれている──。弟子の立川談春(57)と立川志らく(60)が、13回忌の節目に語った。(文中敬称略)【前後編の後編。前編から読む】
「美談を、美談でないように」
今でこそ『芝浜』は落語を代表する人情噺として、ファンの間に広く親しまれている。しかし、そもそもはさほど有名な噺だったわけではない。志らくは「昭和の時代も長いこと、三代目・桂三木助しかやってなかったんです」と明かす。
「三木助師匠の『芝浜』なんて、18分とか20分程度ですよ。その『芝浜』がなんで40分も50分もかかるようなネタになったか。五代目・(三遊亭)圓楽と、談志のせいですよ。2人で寄ってたかって、大ネタにしちゃった。圓楽師匠は客を泣かせるにはいいネタだってことで、噺の中のドラマ性を膨らませて観客も自分も滂沱の涙を流すような噺にした。
逆に談志は美談が嫌いなので、その美談を美談ではないように演じられるのは俺だけだというモチベーションでやっていたんだと思います。この2人に(談志のライバルと称された古今亭)志ん朝師匠も続いた。『俺だったら、こうやるよ』って。圓楽、談志、志ん朝がやってたら、特別な噺になりますよ。芸人にとっても、ファンにとっても」
実際のところ、落語の演目の中で『芝浜』がとびきりおもしろい噺というわけではない。それでもファンならば、年末の落語会で、その日のトリを務める落語家のネタが『芝浜』だとわかると少なからず心が躍ってしまうものだ。俳優の東出昌大も、そんな落語ファンのうちの1人だ。
「落語のよさって、四季を感じられるところだと思うんです。花見の季節だったら『百年目』、夏だったら『青菜』とか。そこへいくと、年の瀬は、やっぱり『芝浜』ですよね。ベートーヴェンの第九と一緒で、今年も終わりなんだなという気分が盛り上がる。畳を新しいのに替えて、いい匂いだな、っていう描写とかが好きなんですよね」
談春も、こう言う。
「『芝浜』のどこがいいの?って言ったら、大晦日の噺だからですよ。除夜の鐘の音だったり、お飾りの笹がふれ合う音だったり。年越しに飲む縁起もののお茶を福茶っていうんだけど、福茶を飲んだり。そして、おかみさんは、そんな大晦日でなければ告白できない話をするわけ。大晦日を舞台にした落語って他にも山のようにあるんですよ。でも、ほとんどが貧乏人の家に借金取りがくる噺。庶民の貧乏人スケッチなんです。でも『芝浜』だけは、幸福スケッチなんですよ」