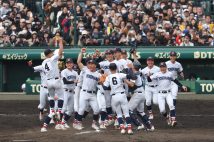奥泉光氏が新作について語る(撮影/朝岡吾郎)
先頃、毎日芸術賞を受賞した『虚史のリズム』は、頁数で1100強。他にも『雪の階』や『グランド・ミステリー』等、500頁級の大長編には事欠かない奥泉光氏の、『虚傳集』は初の短編集だ。
「かつて『神器─軍艦「橿原」殺人事件』(新潮社刊)という大長編の後に『虫樹音楽集』(集英社刊)という、70年代の日本のモダンジャズを巡る連作集を書いたことはあったけど、短編集というのは今作が初めてです。
長いものを書いてると、小説家は物語にまみれてしまう。じつは物語には毒があるから、その毒を解毒したい気分になるんですね。今度の本には短編が5つ入っていますが、それぞれの主人公のことを直接語るのではなくて、その人物について書かれたテクストや証言を構成することで、人物像を間接的に浮かび上がらせる方法をとっている。直接人物や出来事を描き物語るのではない手法や技法に徹したくなったんですね」
本書では第1話「清心館小伝」から最終話の「桂跳ね」まで、主に戦国時代から幕末期を生きた名もなき人々の物語が評伝に近い形で語られてゆく。尤も歴史に埋もれるのはいわば当然。彼らは架空の誰かが架空の書物に記した架空の人物であり、それら虚構の史料にあたる各話の語り手もまた虚構という、まさに何重にも入り組んだ『虚傳集』なのである。
例えば第3話「寶井俊慶」。〈漱石の『夢十夜』に仁王を彫る運慶の話がある。護国寺の山門で仕事をする運慶の鑿使いの巧みさに見物人が感心していると、ひとりの男が、あれは鑿で眉や鼻を彫るのではない、あの通りの眉や鼻が木に埋まっているのをただ堀り出すだけなのだと云う〉云々と、まずは『夢十夜』第六夜を導入に用いたこの一篇では、そこに〈明治の世には運慶のごとき大芸術家を生みだすべき精神がないと嘆ずる、近代批判の文脈〉を求めるより、〈先行テクストの反映を見る〉べきだと主張する〈私〉が語り手を務める。
そして〈木彫石彫とは木や石に埋まる像を堀り出すものであるとの発想を記したテクスト、それも運慶に関わる形で記したテクストは、漱石の同時代たしかに存した〉と続いた時点で、さて次は誰のどんな書物が登場するのかとソワソワしてしまうほど、虚と実との往還が楽しい。
「ヒントになった作品のひとつは谷崎潤一郎の『春琴抄』ですね。僕はあの小説、話自体はあんまり好きじゃない。自分の目を針で突くなんていうのはね(笑)。
しかし文章は素晴らしい。あの中で谷崎は『鵙屋春琴伝』なる架空のテクストを登場させ、その漢字仮名交じりの擬古文を適宜引用しながら、春琴や佐助の生涯を物語っていく。通常の文章のなかに関西弁や擬古文が交錯して、いろいろな声が、音色の異なる楽器のように聞こえてくるのが素晴らしい。懐古文自体の面白さもあります。
芥川龍之介の『藪の中』は『今昔物語』を元ネタにしていますが、僕には『今昔物語』の方が面白い。たぶん古文特有のリズム感ゆえだと思うんです。そうした文体の面白さを自分でも再現できたらという気持ちもありました」
第3話で言えば、霊木に仏の姿を見出すその発想をあの運慶に教わったとする問題の仏師・俊慶に関して語り手の私は、俊慶と縁の深い相州藤沢光沢寺の住職〈亀山董斎〉が記した紀伝『俊慶』及び、その発見者の〈井上啓太郎〉の著作をあたる。そして、実は俊慶について調べ始めたのも学生時代に『遠野物語』を読み、〈天狗隠し〉なる怪異に心惹かれたからだと明かす。
寶井俊慶の名はネットで検索しても〈張型の代名詞〉とあるばかり。私は〈寶井俊慶、生れは一説に紀州田辺〉と書き出される『俊慶』や亀山が元弟子らに直接取材した〈聞き書〉を読み込み、謎多き仏師の生涯に迫るのだ。
面白いのは〈評伝としては「文学臭」が強すぎる〉という井上の『俊慶』評や、〈漱石が「俊慶」を読んだ可能性はまずないが〉と断った上で「俊慶」の記述が漱石に〈間接に届いた可能性〉までは否定しない私の姿勢など、この50頁強の中にも丹念に仕込まれた、著者の洒落や企みであろう。