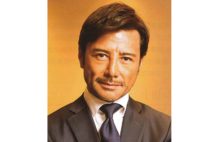パンチョのナポリタン
たらこスパや明太スパは原価が高い。メニューを増やせばオペレーションも煩雑になる。できるだけ短い時間で提供したい。
「『一つのメニューに特化してしまおう』というアイデアが出て、そうすると一つのメニューを何度でも食べたいと思わせなきゃならない。そんな『常習性』を求めていたところ、開発者がナポリタンを得意としていたのです」(野尻氏)
当時の開発者が試作したナポリタンは「すごく美味しい」「毎日でも食べたい」と社内で評判となった。それが「ナポリタン専門店」となった経緯である。
パンチョオリジナルのナポリタンソースは、懐かしいようでいて、唯一無二の味だ。上手く表現できないが、ニンニクが利いているのは確かである。ナポリタンをいろいろなところで食べ歩きながら、時々パンチョで食べてみてほしい。
「パンチョの味」がいかにオリジナルなものであるかわかるはずだ。
「ナポリタンのソースのレシピは社内でも三人しか知らないもので、厳重に管理しています」(野尻氏)
こうして店舗数を伸ばした「スパゲッティーのパンチョ」だが、それは勢いだけではない。ナポリタン愛好家を「ナポリスト」と呼び、世のナポリストの数をもっと増やそうと力を入れている。それこそがスパゲッティナポリタンを国民食として定着させようとする動きだ。
その取り組みの一つが「こども食堂」だ。地域の子供たちや保護者などを対象に食事を提供するコミュニティーとして全国的に広がりを見せているこども食堂。パンチョでは2020年の「パンチョの日」(毎年8月8日にパンチョで食事をするとトッピング券が2枚もらえる)がコロナ禍でテイクアウトのみで行われたが、テイクアウトの容器代を社会還元に充てようと考えたことからこども食堂の事業が始まり、以来定期的にこども食堂でのナポリタン提供を続けている。
「昭和時代から愛されてきたスパゲッティナポリタンの美味しさを次世代に繋げていくためには、未来ある子供たちに知ってもらうというのが一番だと思い、こども食堂での取り組みを始めました。この子たちが大人になって、ナポリタンに愛着を持ってもらえたら、それがさらにその子たちへと繋がっていきますからね」(野尻氏)
「食育」「地域活動」はスパゲッティーのパンチョの使命として、また株式会社パンチョのCSR事業(企業の社会的責任)として、これからも続いていく。
(了。第1回を読む)