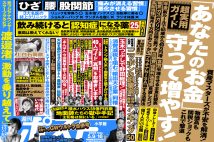『京都の歩き方 歴史小説家50の視点』/新潮社/1760円
【著者インタビュー】澤田瞳子さん/『京都の歩き方 歴史小説家50の視点』/新潮社/1760円
【本の内容】
《観光で訪れる方々がそんな「京都」になにを求めているかを考えるにつけ、生まれも育ちも京都で、今もこの街に暮らしているわたしの目には、観光地・京都と一地方都市たる京都の間にはさまざまな齟齬があるように見えてならない》(「はじめに」より)。研究者として、歴史小説家として、生活者として、京都に生まれ暮らし、京都を見つめてきた著者が、縦横に歩き、自転車で巡って綴った50のエッセイを収録。ガイドブックには載っていない京都のありようが実感として伝わり、京都への見方が変わる一冊だ。
エッセイは自分の驚きを素直に書けるのが楽しい
生八ッ橋の「夕子」は誰の名前なのか? 筆専門店の古い看板が盗まれる事件が起きたが、看板の歴史とは? 歴史小説家が京都を四季折々に綴ったエッセイは、興味深い史実や逸話を紹介しながら、様々な角度から歴史をつたえる。
エッセイは「週刊新潮」に1年間連載された。
「週刊誌の連載は初めてで、本当に試行錯誤の連続でした。1週間が本当に早かった! 書きたい話を見つけて文献にあたり、季節の移ろいを考えて、みたいなことをやるので大変でしたけど、すごく勉強になりました。小説だと咀嚼するのにじっくり時間をかけますが、エッセイは自分の経験をすぐ吐き出す感じで、そのぶん自分の驚きを素直に書けるのが楽しかったです」
澤田さんは大学院で奈良仏教史を研究していたので古代が専門分野になるが、本では様々な時代の出来事が取り上げられており、書き手としての引き出しの多さを感じさせる。
「古代が好きなのは、わからないことが多いから、というのがありまして。知らないことを知りたいという好奇心がとにかく強いので、わからないことを学べるという意味では、どの時代にも興味はあります。日本に限らず、海外の話にも興味は持っていますね」
1年と言わず、何年でも続けられそうですね?と聞くと、澤田さんは「死んでしまいます」と苦笑いした。
「何を書こうかなという、その何かを見つけてテーマをキュッとしぼるのが大変で、そのためには、どこかに出かけて、ウロウロする時間が必要です。御所の中を散歩して休憩中にトンビにご飯を取られるとか、そういうことをいまだにやっていて、その時間をつくろうとすると、どうしても小説を書く時間にしわ寄せがきてしまうんですよ」
身近な題材を入口に、思いもよらない場所に連れて行かれる。澤田さんは、どんなふうに話を組み立てていくのだろう。
「たとえば桜について書こうと思ったら、そういえばこんなエピソードがあった、象にもつなげられる。そうそう足利幕府の時に南蛮船で象が来たんだよね、というふうに話を広げていくんですけど、テーマとテーマ、関心と関心を結びつけてくれるのはやっぱり過去の様々な本ですね」
『日本書紀』や『古今和歌集』から個人の日記や小説も。幅広い分野から、これという印象的な文章が引かれている。