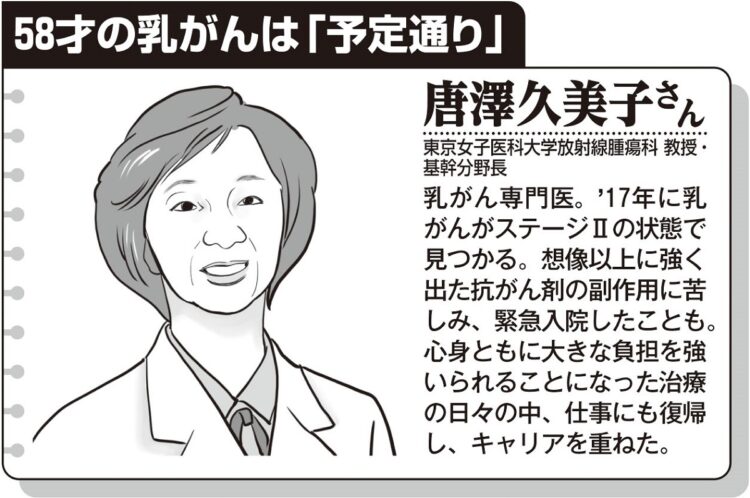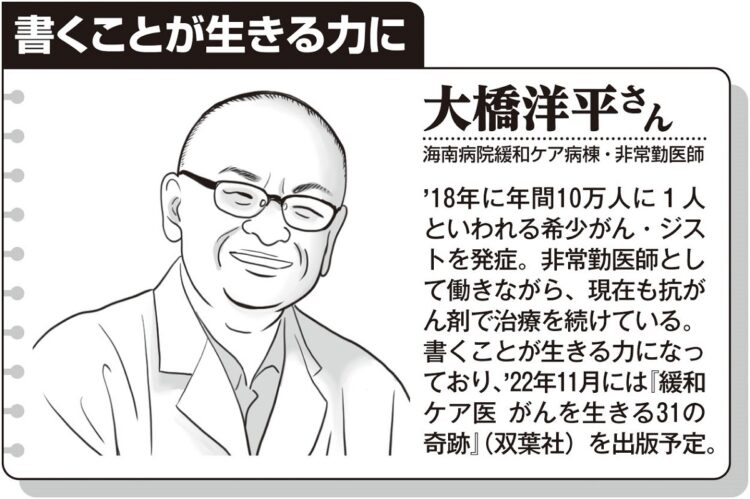唐澤久美子さん
生存率と同様、“余命”という言葉もがんについてまわるが、海南病院緩和ケア病棟の非常勤医師・大橋洋平さん(59才)は闘病を経て、統計上の数値にすぎないと思い至る。
「再発を告げられたとき、ショックで医師に余命を尋ねてしまいました。だけどそれはデータ上の値であって、自分の余命は誰にもわからない。だから『あと何日生きられる』ではなく、転移が見つかった日から『何日生きたか』を足し算する“足し算命”を始めて今日で1292日になります。
非常勤の緩和ケア医として働いてきたため、がんの治療とコロナ禍によって勤務できる日数が減り、収入が激減した時期もありました。ですが、妻の“生きているだけでいいじゃない”という言葉で立ち直れたし、がんになって患者が医師を頼りたい気持ちを強く実感できるようになったいま、自分にできることはもっとあるはずだと思っています」(大橋さん)
医師としての仕事に加え、いまでは自らの経験を執筆して発信することも生きる希望につながっているという。
がんに対峙するときが来たら、5人の「治療方針」をその一助としてほしい。
(了。第1回から読む)
大橋洋平さん
【プロフィール】
小西敏郎さん/東京医療保健大学副学長・医療栄養学科長。消化器のがん手術を中心に行う外科が専門。2007年1月にステージIの胃がんが、2009年にステージIの前立腺がんが見つかり、どちらも手術によって切除した。毎年、年始の検診を習慣づけていたことで、早期に発見できた。
唐澤久美子さん/東京女子医科大学放射線腫瘍科 教授・基幹分野長。乳がん専門医。2017年に乳がんがステージIIの状態で見つかる。想像以上に強く出た抗がん剤の副作用に苦しみ、緊急入院したことも。心身ともに大きな負担を強いられることになった治療の日々の中、仕事にも復帰し、キャリアを重ねた。
大橋洋平さん/海南病院緩和ケア病棟・非常勤医師。2018年に年間10万人に1人といわれる希少がん・ジストを発症。非常勤医師として働きながら、現在も抗がん剤で治療を続けている。書くことが生きる力になっており、2022年11月には『緩和ケア医 がんを生きる31の奇跡』(双葉社)を出版予定。
田所園子さん/緩和ケア医。2010年にステージIの子宮頸がんが見つかり、翌年に全摘出。当時、高知県で3人の子供を育てながら働いていたため、地元で治療を受けることを選択。医師として仕事に復帰してからも、自身の病気を受け入れるのには時間がかかった。
居原田麗さん/麗ビューティー皮フ科クリニック院長。2020年、ステージIの子宮頸がんが判明。その中でも小細胞がんと呼ばれる希少がんであり、広汎子宮全摘出手術をするも2021年に肝臓とリンパへの転移、2022年に腹膜播種が見つかる。現在も治療を続けており、その日々をブログでも発信し大きな反響を得ている。
イラスト/飛鳥幸子
※女性セブン2022年11月3日号