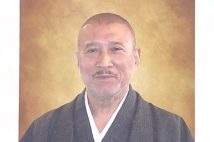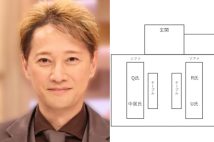元履正社監督として大阪桐蔭と鎬を削った東洋大姫路・岡田龍生監督(産経新聞社)
今の桐蔭には「正直、怖さはないです」
昨春のセンバツでは準々決勝で西谷監督の母校である報徳学園(兵庫)に1対4で敗退し、昨夏は2回戦で石川の小松大谷と対戦。相手の軟投派エースに為すすべなく、たったの92球で完封を許した。勝つ時は豪快に打ち勝ち、敗れる時は劇的に華々しく聖地に散る。そんな戦いを続けてきた大阪桐蔭が、実にあっさりと甲子園で敗れることが続いている。
そして、前述したように昨秋は大阪大会で準優勝したとはいえ近畿大会で1勝もできなかった。
大阪桐蔭が最後に全国制覇を遂げたのは2022年春だ。それからおよそ3年の間に起きた高校野球の大きな変化というと、新基準となる低反発バットの導入である。
身体能力に長けた将来有望な中学生が全国から集まってきていた大阪桐蔭は、真芯にしっかりミートしなければ外野フェンスどころか外野手の頭を越えることが少ない低反発バットの影響をもっとも受けた学校かもしれない。ビッグイニングを作ってゲームを優位に進め、相手の戦意を喪失させるような試合は少なくなり、ここ数年は守備の不安も拭いきれない。
昨春の大阪大会準決勝で大阪桐蔭を破った大阪学院大高校の辻盛英一監督は言う。
「近畿大会の戦いなどを見ていて、うちが勝てるかどうかは別として、以前ほどの怖さはないですね。これは私に限らず、みなさんが思っていることだと思うんですが、桐蔭の強さを支えているのは、圧倒的スカウト力やと思うんです。決して、育成力が高いわけではない。良い選手が入学しなくなるようなことがあれば、だんだんと勝つことができなくなるのではないかというのが正直な印象です」
一方で、2021年まで履正社を率いていた岡田龍生監督(現・東洋大姫路監督)は、かつてのライバルの直近の戦いぶりについて、こう話した。
「大阪桐蔭の野球が大きく変わったという印象はありません。僕は(昨年夏の)小松大谷との試合のテレビ解説を担当しましたが、確かにこれまでだったら頭を越えていたかもしれない当たりを捕られたりもしていた。だからといって、単純にバットを振り回しているだけでなく、しっかりとボールをとらえようとする姿勢は感じられます。相変わらず、能力の高い選手が揃っているとも思います」
甲子園で勝てなくなってきているとはいえ、全国屈指の激戦区である大阪を勝ち抜く地力までなくなっているわけではない。しかし、その大阪でも勢力図に大きな変化が起き始めているのである。
(大阪桐蔭、履正社を脅かす高校をレポートした第2回に続く)
■取材・文/柳川悠二(ノンフィクションライター)