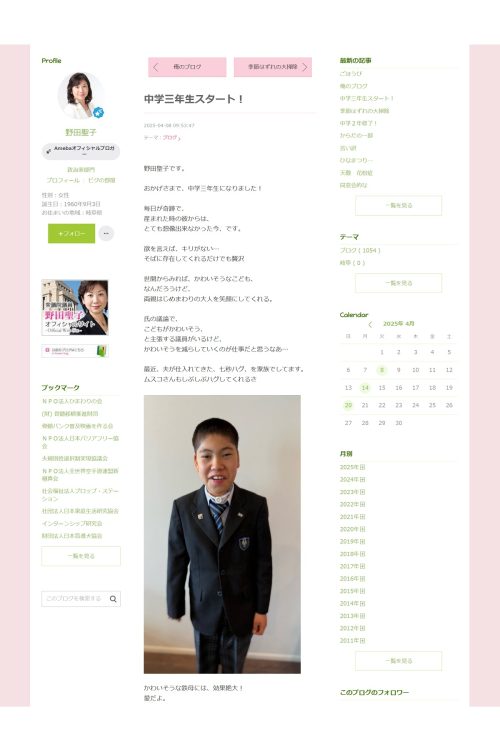50歳で出産した野田聖子「50歳で産まざるを得なかった原因は性教育です」(SNSより)
「避妊しないと妊娠してしまう」が招く“誤った感覚”
今、卵子凍結を検討したり、妊活や不妊治療に向き合っている世代は、「望まない妊娠を避ける」や「性感染症にならないため」の性教育を受けて育っている。これによって、「避妊しないと妊娠してしまうから注意を」=「妊娠は、簡単にできるもの」という誤った感覚が育ったという声も少なくない。
私自身、35歳を超えてからも、“避妊をやめたらすぐに妊娠するだろう”という認識がどこかにあった。いざ妊活をスタートして初めて、「妊娠ってこんなにしづらいものだと知った」という声が少なくない理由は、「望まない妊娠を避ける」や「性感染症にならないため」の性教育しか受けてこなかった影響が大きいと言えるのではないだろうか。妊娠・出産にまつわる知識は、とても大切なことであるはずなのに、自分から調べないと得られない情報になっている現状がある。
「これだけ不妊治療を受ける人が増えているのだから、“避妊”だけではなく、“不妊”の教育も必要」「生物学的な適齢期をきちんと認識した上で、ライフプランや選択肢を考えられるようにしていくべき」と話す不妊治療クリニックの医師も多い。
日本の教育課程では、中学1年生の時に、受精や妊娠を学び、成長に伴い男女の身体がどのように成熟していくかや、ヒトの受精卵が胎内でどう成長するのかを教える。しかし教科書には、受精の前提となる性交についての記述はない。理由は、国が定める学習指導要領に「妊娠の経過は取り扱わないものとする」という一文があるためで、これが通称「はどめ規定」と呼ばれている。いわば“妊娠の過程=性交については取り扱わない”とするルールのことだ。
対して諸外国はどうか。性交や避妊方法について、ドイツでは小学校高学年で、フランスやオランダ、フィンランドでは中学校で教える(『教科書にみる世界の性教育』かもがわ出版、2018年)。
2009年にユネスコが公開した包括的性教育の指針「国際セクシュアリティ教育ガイダンス(2018年に改訂)」の生殖に関する項目では、5~8歳の段階で「赤ちゃんがどこから来るのか、妊娠の基本的な仕組みについてを説明できる」ことを目標にしている。さらに9~12歳になると、「どのように妊娠するのか、どのように妊娠を避けることができるのかについて説明でき、基本的な避妊方法について確認することができる」ことが目標とされている。世界の中で、日本の性教育がいかに遅れているかが如実に表れていると言える。