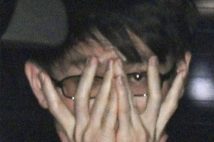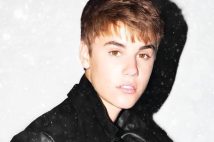ご家族揃って車いすバスケを観戦された(2025年2月、東京・渋谷区)
1月27日、日本政府は国連への拠出金を、「女性差別撤廃委員会」の活動に使わないよう求めた。昨年10月、同委員会が皇室典範について「皇位継承における男女平等を保証するよう改正すべき」と勧告したことへの対抗措置だった。
現行の皇室典範では、《皇位は、皇統に属する男系の男子たる皇族が、これを継承する》と規定されている。それが国連の委員会には「皇室は女性差別」と映ったわけだ。
「勧告では、男女平等のために王位継承法を改正した他国の事例が挙げられました。勧告を受けて議論が進めば、『愛子天皇』が実現する可能性もあったでしょう」(皇室ジャーナリスト)
日本政府が国連に強硬なファイティングポーズを取った背景を、皇室制度に詳しい元衆院議員で弁護士の菅野志桜里さんが読み解く。
「女性の皇位継承の問題について、これまで政府として真摯に対応してきていれば、お金の使途を制限するという敵対的な手段ではなく、“しっかりと問題解決に向けて国会や国民全体で議論しているので、国連から非難される言われはない”と堂々と説明できたと思います。
しかし実際には、女性の皇位継承の問題を、『皇族数の確保』問題にすり替えて、本質的な議論を先送りしてきたわけです。自分たちが正面から取り組んでいないことに負い目を感じているから、そうした外からの“耳が痛い指摘”に対して威嚇的な対応につながったのでしょう。現行制度が女性差別に該当しないと言い切るなら、せめて女性皇族に対して“生きづらさ”を強いている構造的な圧力や課題を解決する努力をすべきです」
現在、国会で議論されている「皇族数の確保」案こそ、実は、愛子さまや秋篠宮家の次女・佳子さまなど、未婚の女性皇族をさらに苦しめかねない内容なのだ。
衆参両院は1月末、皇族数の確保策に関する協議を再開した。焦点は、「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持できるようにするかどうか」だ。それについて、協議の場では「3月にかけて複数回の全体会合を開く」という方針が示され、早ければ4月にも何らかの結論が示されることになる。
「女性皇族が結婚後も皇室に残る案は、現時点でも与野党各党のおおむねの賛同を得られており、合意に至るのはほぼ間違いないとみられています。ただ、それをもって“愛子さまの将来がようやく安定する”というのは早合点です。このままいけば、愛子さまが限りなく結婚されにくい状況を作り出してしまうのです」(宮内庁関係者)