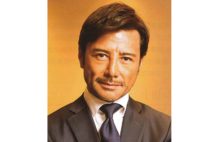のと鉄道能登鹿島駅。穴水町にある同駅は「能登さくら駅」という愛称を持つ桜の名所(時事通信フォト)
「行って応援!乗って応援!現地消費型ふるさと納税 鉄道があるまち応援プロジェクト」という副題がつけられている「テツふる」は、その沿線地域の活性化を目指すプロジェクトに特化した地域振興の取り組みとして3月に始まったばかりだ。ライターの小川裕夫氏が、「テツふる」が持つ他のふるさと納税と異なる特色や、期待される効果についてレポートする。
* * *
すっかり定着したふるさと納税は、2008年の税制改正によって導入された。複雑な仕組みだったこともありスタート時は低調だったが、地方の市町村がマグロやカニ、和牛といった豪華な特産品を返礼品として用意して注目を集めるようになった。自治体関係者や地方自治の研究者から皮肉を込めて “ふるさと納税は官製ネット通販”と呼ばれることもあるが、自治体に還元できる仕組みとして有効活用を模索する動きもある。そのひとつが”テツふる”だ。
鉄道沿線に特化したふるさと納税というアイデアは、どんな経緯で生まれたのか。
「鉄印帳」から「テツふる」へ
「弊社は2020年に旅行代理店の読売旅行・日本旅行と協力し、第3セクター40社が参加した『鉄印帳』という取り組みをスタートさせています。鉄印帳はご朱印帳の鉄道版ともいえるもので、多くの人たちが実際に地方鉄道まで足を運び、乗るという企画です。少しでも地方鉄道を支援したいという思いから鉄印帳は始まったわけですが、2025年は鉄印帳を始めてから5年になります。そんな節目に何か新しいことができないかと考え、今度はふるさと納税の鉄道版ともいえる “テツふる”を始めることになりました」と説明するのは、テツふるの管理・運営をしている旅行読売出版社メディアプロモーション部の担当者だ。
テツふるを簡単に表現すれば、人口減少で危機に瀕する地方の鉄道を支援するためことを目的としたふるさと納税ということになる。ふるさと納税というとマグロやカニ、和牛といった地域の特産品が人気の返礼品となってきたため、名産品がない地域や都市部には無関係と思われてきた。
ところが、JR東日本の通販サイトJREモールにふるさと納税の返礼品として「新宿駅駅長体験」を用意したことが話題になり、いわゆる贈答品としてのモノでもなく、コトによる返礼品でもふるさと納税を集められる可能性が開かれていった。