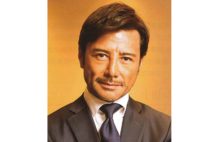「テツふる」利用の流れ(「テツふる」資料より)
もっとも、JR東日本の鉄道資産をフル活用した返礼品は、話題になった「1日駅長体験」(新宿駅)や「ポイント転換&入換車両乗車体験」(小淵沢駅)など、JR東日本という充実した鉄道インフラを有する巨大企業だからこそ可能と言えるものだろう。一方で “テツふる”は、地方都市と鉄道を組み合わせた、より地域の生活や環境に沿った意欲的な取り組みでもある。
2020年に発売された鉄印帳はコロナ禍で苦境に立たされた第3セクター鉄道の救世主になり、発売された初版5000部はすぐに発売。鉄道ファンのみならず幅広い層から支持を得て、その後も順調に増刷を重ねた。そして、2025年3月までに7万2000冊を売り上げている。
コロナ収束後、訪日外国人観光客をはじめ日本人の間でも旅行需要が復調している。人気の観光地ではオーバーツーリズムが問題視されるようにもなっているが、そうした観光客が殺到するのは東京・京都・大阪など大都市や有名観光地に偏る傾向があり、地方都市・ローカル線は経済的な恩恵が少ない。
鉄印帳が地方鉄道への誘客に果たした功績は大きいが、いまだ地方の鉄道は苦しい状況にある。なにより、沿線人口が加速度的に減少していることから、廃線などの検討も始まっている。
「鉄印帳は2024年3月からデジタル版を開始しましたが、デジタル化に取り組む中で地方鉄道を新しい形で支援できるのではないかと考えました。そこから生まれたのが”テツふる”です。鉄印帳は第3セクターの鉄道会社を支援するものですが、ふるさと納税は沿線自治体への寄付という扱いになります。そのため、テツふるは第3セクターの鉄道に限定していません。JRの路線でも、鉄道が走っている自治体なら支援できる仕組みです」(同)
現地を訪れて使用することが前提
“テツふる”第一弾は、2025年3月から石川県穴水町と鳥取県の若桜町の2町でスタートした。穴水町は2024年の能登半島地震で大きな被害を出したが、町内を走るのと鉄道はその復興のシンボルとして地域住民に勇気を与えている。若桜鉄道は沿線に鉄道遺産が数多く残り、町民が一丸となって鉄道を残そうという熱意に溢れている。どちらの町も、テツふる第一弾に相応しく、鉄道と濃密な関係を築いてきた自治体でもある。
「テツふるを通じてふるさと納税をすると、金額の30パーセントに相当するデジタル商品券が返礼品として即時発行されます。旅行で現地まで足を運んでもらい、地元の料理やお土産をデジタル商品券で購入してもらう。それが地方のローカル線を経済的に支える一助になります」(同)