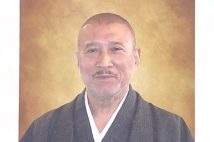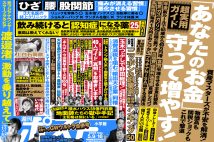1994年2月、カリフォルニアから輸入されたコメの販売(時事通信フォト)
「備蓄米放出がまったく機能していない、これからも放出すると言っても効果がないことが不気味ですね。政府はもうそういった能力を失いかけているのではというか、実は機能してないんじゃないか、そう思わされてしまう。そして政府の失策のつけを消費者に押しつけるようなことを大臣が平気で言う」
これは筆者旧知の食品専門商社のバイヤーも同様のことを語っている。「近年の政府の食料政策はヤバいを通り越している」として、
「知識がないのか官僚の言いなりなのか、自民党の食料政策が裏目裏目に出ている、結果として食料自給率が下がるような政策をとっている。口では食料自給率を上げる、農家を守ると言っているが、やってることは買い負けと抜港(コンテナ船などが日本の港を避けること)を招いている。日本そのものに力がなくなったからと言うなら、ではその原因は政府とその裏にいる官僚としか言いようが無くなる」
強い言い方だが彼は財務省の名も出した。農水省の話になぜ、となる向きもあるだろうが結局のところ食料問題も財務省の意向が絶大だという。輸出入米に絡む問題でこれから大きな騒動になるかもしれないとも。なるほど財務省が国交省から自賠責積立金約6000億円を借りパクしている問題もそうだが、農水省もまた強くは出られないということか。自公の政治家すら。
それにしても、なぜ昨年の政府の予想がことごとく外れるほどにコメが不足し、コメの値段が上がり続けているのか、ようやく放出した備蓄米も効果は薄い。いずれ効果が出るというにはオオカミ少年が過ぎる。
実際問題、買い占めるほど店頭にはないし実際、そこまでのパニックはない。ただコメが高くなり生活が苦しくなるばかり。輸送問題や農協問題など言われるがそればかりでもないように思う。転売ヤーなど忌々しいが巨大なコメ市場からすればごく限定的だ。
コメはどこに消えた。
江藤農水大臣の言う「最終消費者」のほとんどの感想はそれしかない。備蓄米すらスーパー等に0.3%しか流通していない状況で消費者に責任転嫁されても、である。
日野百草(ひの・ひゃくそう)/出版社勤務を経て、内外の社会問題や社会倫理、近現代史のルポルタージュを手掛ける。日本ペンクラブ広報委員会委員。