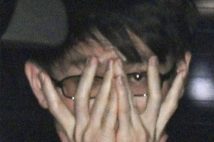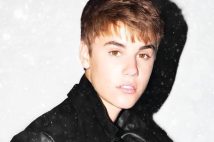そもそも「官軍・賊軍」などという区別は絶対的なものでは無く、政見の違いによる便宜上のものだ、としたのもそのためだ。そうすれば殉難者は朝敵では無くなり、その魂は安らかな眠りにつくことができる。しかし、それは先ほども述べたように天皇への批判と取られかねない。だから、祭文の最後で「赤誠を披瀝」つまり自分は天皇への熱烈な忠誠心があることを包み隠さず述べる必要があったのである。
こうした原の心情がわかれば、爵位を受けなかった理由もわかる。一口に言えば、「平民」であることを誇りに思ったから、では決して無い。じつは、明治以降昭和二十年までの日本人の身分には三つの評価基準があった。爵位のほかに勲位と位階である。
位階は律令制度施行以来千数百年にわたって続けられた伝統ある制度で、「正一位」とか「従三位」などといったものである。また勲位も起源は古く、国家に対してどのような功績があったかを「勲一等」をトップにランク付けするものである。これに対して爵位(華族制度)は一番歴史が浅く、制定された明治十七年当時は明治維新でどれだけ功があったかが基準とされていた。
たとえば、明治までは足軽だった伊藤博文が最高位の公爵になったのに対し、大名では伊達家の本家仙台藩が伯爵にしかなれなかったのに、その分家の宇和島藩伊達家は一階上の侯爵になった。宇和島藩は維新にさまざまな功績があったのに対し、仙台藩は奥羽越列藩同盟に味方した「賊軍」であったからだ。原にしてみれば、こうした「不公平」が腹立たしかったのではないか。
その証拠と言うべきか原は頑なに爵位を受けることは拒否したが、位階と勲位は受けている。彼は「正二位大勲位」である。ちなみに大勲位とは勲一等を越える勲功を挙げた者への敬称で、勲章の大勲位菊花大綬章かその上の大勲位菊花章頸飾が天皇から授与される。頸飾とは文化勲章のように首からペンダントのようにぶら下げる勲章のことで、最近では暗殺された安倍晋三元首相が「大勲位」を受勲している。
ただ、原敬は遺書で「墓標には位階勲等も書くな」と指示している。なぜ自殺したわけでも無いのに遺書が残されているのかということについては後ほど説明するが、古くからの制度ということで受けた位階勲等についても墓碑への記載を拒否したのはなぜか? それは、たとえば伊藤博文が原より上の従一位なのは、あきらかに維新における「賊軍討伐」の功が含まれているからであり、それがあるのに後世の人間に「伊藤よりは下なんだ」と思われるのが嫌だったのだろう。
語弊はあるかもしれないが、原を支えていたのはあきらかに庶民派としての感覚では無く、傷つけられたエリート意識ではなかったか。そうでなければ、わざわざ「一山」と号しないだろう。しかしこのことは、じつは不幸も招いた。
それはなぜか。